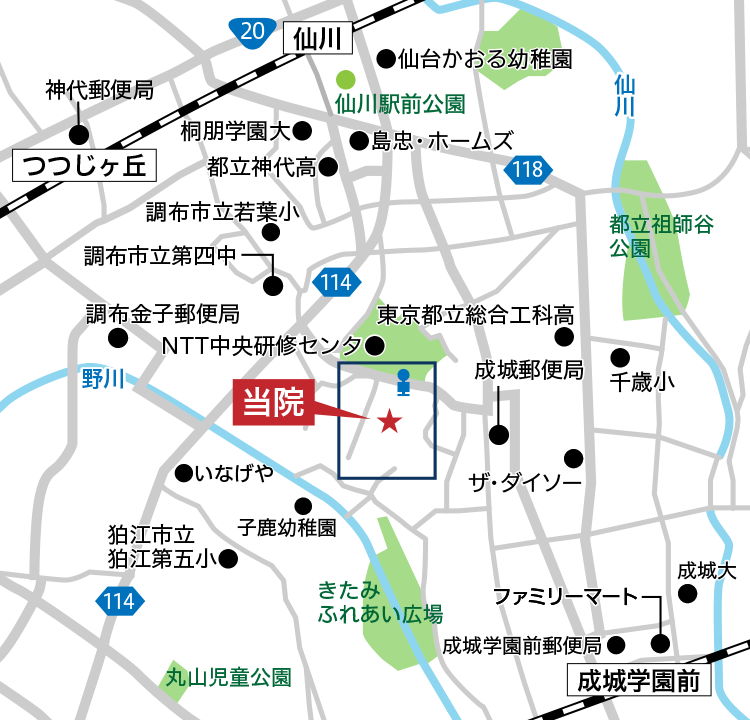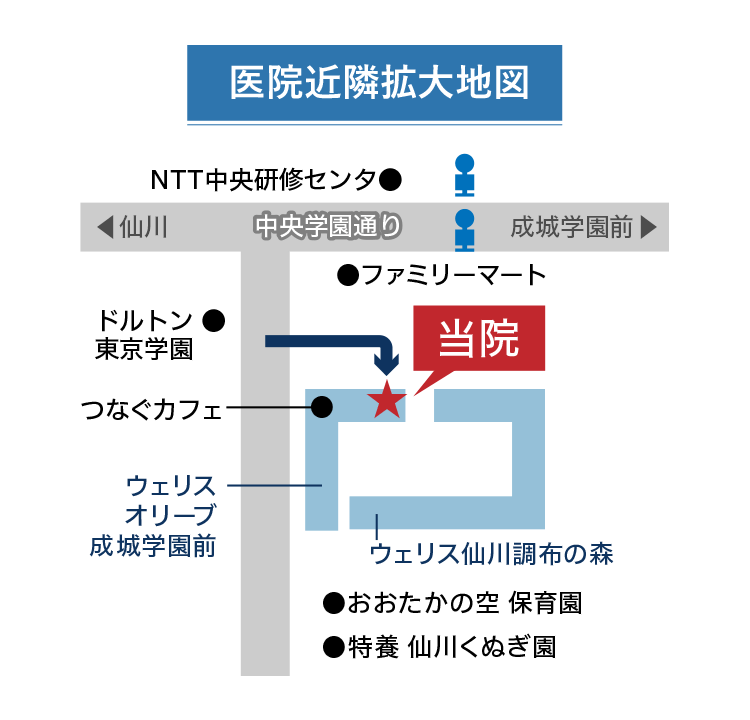整形外科とは
整形外科では、運動を行うのに必要な組織(=骨、軟骨、筋、靭帯、神経など)の病気・ケガを診察、検査、治療を行います。
扱う器官は、脊椎(脊柱)・脊髄、骨盤、上肢(肩、肘、手、手指)、下肢(股、膝、足、足指)など広範囲にわります。また、年齢も子どもから高齢者まで、すべての年齢層が対象になります。
このような症状はご相談ください(例)
- 腕、足、腰などが痛い
- 首が痛い、肩こりがある
- 手や足のしびれがある
- 骨折や脱臼を繰り返している
- 転倒しやすいので、骨折のリスク(骨粗鬆症)を知りたい
- 関節リウマチによる痛みがある
整形外科で扱う主な疾患
- 外傷(ケガ)
- 打撲、捻挫
- 骨折、脱臼
- 関節痛(肩、腕、足、腰など)
- 五十肩(肩関節周囲炎)
- 脊柱管狭窄症
- 腰椎椎間板ヘルニア
- 変形性膝関節症
- 関節リウマチ
- 骨粗鬆症
- ロコモティブシンドローム
整形外科でよくみる疾患
五十肩(肩関節周囲炎)
五十肩(肩関節周囲炎)とは、肩の関節が痛んで、関節が動きづらくなる病気です。中高年、特に50歳代で発症します。主な原因は、加齢とともに肩の関節を作る骨や軟骨、靭帯や腱などに炎症が起きることといわれています。
症状としては、着替えや、腕を伸ばすなど生活動作の中で肩を動かしたときに激しい痛みを感じたり(運動痛)や、夜中に肩にズキズキとした痛みを感じたり(夜間痛)します。肩関節の炎症が治まってくると痛みも軽くなりますが、炎症によって肩の関節とその周辺が癒着したり、肩を動かさないと血流が悪くなったりすることで、関節の動きが悪くなってしまうこともあります。
検査では、痛みのある部位のレントゲン撮影や、MRI検査などを行います。
治療は、痛み・炎症を治めるため、痛みが強い時期は重いものを持ったり、腕を上げたりする動作を控え、消炎鎮痛剤の内服や湿布を使います。炎症を抑えるステロイドやヒアルロン酸の関節注射を行うこともあります。強い痛み・炎症がおさまったら、温熱療法により血行を良くし、肩を少しずつ動かして、肩の動く範囲を回復いきます。
脊柱管狭窄症
脊柱管狭窄症は、背筋を伸ばして立ったり歩いたりすると、下肢にしびれや痛み(坐骨神経痛)が出て歩きづらくなる病気です。前かがみになると痛みが軽減されます。
脊髄(神経)は、背骨、椎間板、関節、黄色靱帯が囲んでいるトンネル(脊柱管)を通り、運動指令や感覚情報を伝えています。脊柱管狭窄症では、加齢・病気などにより、椎間板の変形・突出や、黄色靱帯が厚くなることで神経が圧迫され、下肢のしびれや痛みが出ます。
検査では、腰のレントゲン撮影や、MRI検査などを行います。
治療は、姿勢を正しく保ったり、リハビリ、コルセット装着、鎮痛剤、血流を改善する薬、神経ブロック注射などが行われます。日常生活に支障が出るほど症状が悪化する場合には、手術が行われることもあります。
椎間板ヘルニア
椎間板ヘルニアは、腰やおしりが痛み、下肢にしびれや痛み(坐骨神経痛)が出たり、足に力が入りにくくなる病気です。
加齢、悪い姿勢での動作や作業、喫煙などが誘因となり、椎間板が突出して脊髄を圧迫することで症状が出ます。
検査では、下肢伸展挙上試験(膝を伸ばしたまま下肢を挙上し、坐骨神経痛の症状が出るかを調べる)や、下肢の感覚、筋力を調べます。レントゲン撮影、MRI検査なども行われます。
治療は、痛みが強い時は腰を温め、安静、コルセット装着、鎮痛剤の内服・湿布、神経ブロック注射などが行われます。症状が強い場合や、下肢の脱力、排尿障害などもみられるときは、手術が行われることもあります。
骨粗鬆症(こつそしょうしょう)とは

骨は、一度できあがるとそのまま変わらないように思われがちですが、実は壊されたり作られたりといった新陳代謝を常にくりかえしています。骨を壊す働き(骨吸収)と骨を作る働き(骨形成)がうまくバランスをとることで、適切な強度で同じ形の骨が維持されているのです。
骨粗鬆症では、何らかの原因によって骨吸収と骨形成のバランスが崩れて、骨の強度(骨密度)が弱く・もろくなり、骨折しやすくなる病気です。
とくに閉経後の女性や高齢者に発症しやすいと言われています。
また、骨は適度な負荷を受けることで骨形成が進みますので、運動不足も骨が弱くなりやすいです。
その他、喫煙、飲酒なども骨粗鬆症のリスクとなります。
骨粗鬆症の原因
骨粗鬆症の約9割は原発性骨粗鬆症で、残り1割はその他の病気によって二次的に起こる続発性骨粗鬆症です。
原発性骨粗鬆症の大半は、閉経後の女性に起こるもの(閉経後骨粗鬆症)と高齢者(老人性骨粗鬆症)が占めています。
閉経後骨粗鬆症
女性ホルモンの一つであるエストロゲンには、骨吸収(骨を壊す働き)のスピードを緩める効果がありますが、閉経を迎えると分泌量が減っていきます。
そのため、閉経後は骨吸収のスピードが加速し、骨形成が追いつかなくなって骨は鬆(す)が入ったようなスカスカ状態となって、もろくなっていくのです。
また極端なダイエットなどによって女性ホルモンのバランスが崩れると、閉経前の女性であっても骨粗鬆症になることがあります。
老人性骨粗鬆症
加齢に伴って、食事量が減ることでカルシウムの摂取量が減ったり、腸からカルシウムが吸収されにくくなったり、カルシウムの吸収を助けるビタミンDの合成が減ったりすることで、骨粗鬆症が起こります。
また、外出や運動量が減ることでも骨粗鬆症が進みやすくなります。
続発性骨粗鬆症
特定の病気(関節リウマチ、副甲状腺機能亢進症、糖尿病、慢性腎臓病、動脈硬化、慢性閉塞性肺疾患〔COPD〕など)や、薬の副作用(ステロイド薬の長期服用、ホルモン治療など)が原因でも、骨吸収と骨形成のバランスが崩れて、骨粗鬆症となることがあります。
骨粗鬆症の症状
骨密度や骨量(骨の主成分であるカルシウムなど)が低下するだけでは特に症状が現れることはありません。
そのため、骨粗鬆症になっていることに気づかずに症状を進行させるようになります。
そして、何かのはずみでつまずいた時などに骨折し、その際に骨粗鬆症と診断されることが多いです。
骨粗鬆症の方で骨折しやすい箇所は、手首、脚のつけ根(大腿骨近位部)、背骨(脊椎)などがあります。
脚のつけ根を骨折すると寝たきり状態になったり、大きな手術が必要になったりすることもあるので要注意です。
ぶつかったり転倒したりすることをきっかけで骨折することが多いですが、特にぶつけたりしていなくても、自身の体重の負荷によって脊椎圧迫骨折を起こしてしまうこともあります。
なお、これといった症状はないものの、主に高齢者の方や閉経後の女性で、身長が縮んできた、背中が丸まってきた、背中や腰が痛んだり重く感じる、膝が痛いなどの症状があれば、骨粗鬆症により骨折を起こしている可能性がありますので、検査を受けられることをお勧めします。
骨粗鬆症の検査
骨粗鬆症が疑われる場合、診断をつけるための検査が行われますが、その方法として以下のようなものがあります。
骨密度検査
骨の密度を調べ、骨の強さを確認します。
骨密度検査にはDEXA法、SEXA法、MD法、DIP法、超音波法など様々な方法がありますが、当院では低被曝で簡便・迅速に行えるDIP法で骨密度検査を行っています。
20~44歳の健康な成人の骨密度を100%としたときの骨密度(骨密度若年成人平均値〔YAM; Young Adult Mean〕)を計測し、YAM 70%未満と判定された場合、骨粗鬆症と診断されます。
骨代謝マーカーの検査(血液検査、尿検査)
血液や尿によって、骨代謝の指標である骨代謝マーカーの値を測定し、骨吸収と骨形成のバランスを確認します。
骨代謝のバランスが崩れている場合は、骨が弱くなっている可能性があります。
レントゲン検査(X線撮影)
背骨(主に胸椎や腰椎)をX線撮影し、骨折や変形の有無を調べるほか、まるで鬆(す)が入ったかのように骨がスカスカした状態になっていないかも確認します。
身長測定
主に25歳時の身長と比較し、どれほど身長が縮んでいるかを調べます。
25歳時より4cm以上低い場合は、骨粗鬆症が疑われます。
骨粗鬆症の治療・予防
骨粗鬆症の発症原因については、老化や閉経による影響だけではありません。
日頃の食事や運動、喫煙、飲酒などの生活習慣も大きく関係することから、この病気は「骨の生活習慣病」とも呼ばれています。そのため、食事療法、運動療法、禁煙も、骨粗鬆症の予防と改善には欠かせません。
食事療法
よい骨を維持するために必要な栄養素は、骨の主成分であるカルシウムやたんぱく質と、カルシウムの吸収を助けるビタミンD、骨の代謝に必要なビタミンKなどです。
カルシウムは食品として700~800mg/日、ビタミンDは400~800IU/日、ビタミンKは250~300μg/日を摂取することが推奨されています。
これらの栄養素を積極的に摂りながら、バランスのとれた食生活を心がけましょう。
また、過度な喫煙や飲酒はカルシウムの吸収を妨げてしまうので、できる限り控えるようにしてください。
※カルシウムを摂り過ぎることにより尿路結石などの病気を起こすことがありますので、適切な量を摂取するようにしましょう。
積極的に摂取しておきたい栄養素を多く含む食品
カルシウム
- 牛乳
- 乳製品
- 干しえび
- しらす
- ひじき
- わかさぎ
- いわし
- ししゃも
- 大豆製品
- えんどう豆
- 小松菜
- モロヘイヤ
など
たんぱく質
- 肉類
- 魚類
- 卵
- 乳製品
- 大豆製品
など
ビタミンD
- あんこうの肝
- しらす干し
- いわしの丸干し
- すじこ
- 鮭
- さんま
- かれい
- うなぎ
- 煮干し
- 干し椎茸
- きくらげ
など
ビタミンK
- 納豆
- 抹茶
- ブロッコリー
- きゃべつ
- サニーレタス
- モロヘイヤ
- しゅんぎく
- おかひじき
- 小松菜
- ほうれん草
- 菜の花
- かいわれ大根
- にら
など
運動療法
骨を支えているのが筋肉です。
そのため、日頃から運動などによって筋肉を鍛えておくことで、体をしっかり支えられるようになって、バランス感覚も向上していき、転倒防止にもつながります。
なお、骨量を増やす運動量ですが、強い負荷をかける必要はなく、息がはずむ程度の有酸素運動で充分です。
具体的には、ウォーキングであれば1回30分程度です。
できれば週3回以上、継続的に行うようにしてください。
薬物療法
生活習慣の改善だけで治療や予防につながらない場合は、併せて薬物療法も行います。
骨粗鬆症の治療薬として、骨の破壊を抑制する薬(ビスフォスフォネート製剤、選択的エストロゲン受容体調整薬〔SERM〕、デノスマブ)、骨の材料を補う薬(カルシウム製剤、活性型ビタミンD3製剤、ビタミンK製剤)、骨をつくる薬(副甲状腺ホルモン製剤)などがあります。